
もう25年以上前のことになりますが、当時私が付き合っていた女性は、大の音楽ファンでファンクが好きでベーシストでもありました。
ベースはスラップ(日本風に言えば「チョッパー」ですね)ビシバシキメて、それなりに本格的なファンク系のバンドのメンバー。今思い出しても、結構な腕前でした。その彼女から教わった音楽のひとつに、スライ&ザ・ファミリー・ストーンがありました。
今回は、そのsly&the famiky stoneについて書いてみたいと思います。
スライ&ザ・ファミリー・ストーンとは
スライ&ザ・ファミリー・ストーンとは、60年代後半から70年代後半ぐらいまで活躍したサンフランシスコ出身のファンクバンドです。
1960年代半ば頃にサンフランシスコでラジオDJをしていた、スライ・ストーン(本名:シルベスター・ステュワート)が中心となってデビューしたスライ&ザ・ファミリー・ストーン、1968年にリリースした「ダンス・トゥ・ザ・ミュージック」で火が点き、同年に出した「エブリデイ・ピープル」が全米No.1を獲得し、人気を確実のものとしました。
その後にも「スタンド」「サンキュー」「ファミリー・アフェア」などヒット曲を出し続けていきます。
スライ&ザ・ファミリー・ストーンのメンバーには、『スラップ奏法』を編み出したと言われるベーシスト、ラリー・グラハムがいましたが、知った当時は私はそういったサウンド的なものよりも、当時のアメリカの時代背景と共に、バンドの成り立ちとか歌われている内容の方に興味を持ちました。
スライ&ザ・ファミリー・ストーンの本質とは
スライ&ザ・ファミリー・ストーンは、一言でいえばファンクバンドといえるのかもしれませんが、「ファンクバンド」と一言で済ますのは物足りなさすぎるのだと思います。
特に初期のころは、サザンソウルだったりロックだったりですし、一連のヒット曲はその上で極上のポップセンスも持ち合わせており、いくつかの音楽のクロスオーバー感が目立ちます。
さらに言えば、男女混合であり、白人と黒人の混合バンド。60年代後半でこのクロスオーバー感、非常に先進的なのかなと感じます。
サウンド面よりも、男女混合、白人黒人混合というのが、このバンドのポイントといいますか、本質のような気がしています、まあ個人的意見ですけどね。
その辺は後述します。
“I Have a Dream”とは異なる理想
スライ&ザ・ファミリー・ストーンが活動していた当時のアメリカは、黒人公民権運動が盛り上がっていた時期で、マーティン・ルーサー・キング牧師のあの有名なスピーチでの「I Have a Dream」もこの時期です。
ソウルミュージックも「Black Is Beautiful」の思想がが根幹に流れていますので、どちらかというと公民権運動の考えに近いです。
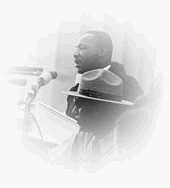
ファンク(ソウルのいちジャンル)ロックというジャンルを築いたスライも、その流れを汲んだとしてもなんら不思議ではないし、そちらの方が自然ですが、スライは違いました。
スライが掲げた白人と黒人、男と女、ソウルとロックを混合は、ひとつの理想であって、それは黒人公民権運動のコンセプトとは異なるものです。
「Don`t Call Me Nigger,Whitey」で言いたいこと
アルバム『Stand!』の中に「Don`t Call Me Nigger,Whitey」という曲があります。
俺を黒人と呼ぶな、白人どもよ
というわけですが、
「Don`t Call Me Whitey,Nigger」という歌詞も交互に出てきます。
つまり、白人と黒人が肌の色の違いで侮蔑するのはお互いに愚かなことだ、ということを言いたいのでしょう。
名曲「Everyday People」の歌詞に込められたメッセージ
また、同アルバムに「Everyday People」という曲があります。この曲の一節「Different Strokes,For Different Folkes」とは、「十人十色」という意味だそうですが、これだって、
「人はみんな違うんだから人種差別なんて意味がない」と言っているようなものです。
スライは「スライ&ザ・ファミリー・ストーン」という一つの小さなコミュニティを、アメリカ合衆国に例えて、あるべき理想をメッセージとして発信していたのだと思います。
※この「Everyday People」の訳詞について、非常に面白い記事があります。CDのライナーノーツの訳詞はどうもトンチンカンなようで、こちらの訳の方がより原詞に近い訳だと思います。
「サンキュー」で露呈したスライの疲弊
1969年に、『Greatest Hits』が発売しましたが、そのアルバムのラストナンバーに「Thank You(Falettinme Be Mice Elf Agin)」という曲が収録されていますが、その曲の一節にこんな部分があります。
本当の自分に戻してくれたことに感謝するよ ~(中略)~
パーティありがとう。でも、もうここには居れないんだ
色んなアイデアがあるからね
スライは疲れていた?
こんな言葉を残した翌年1971年のスライはエラい変わりようでした。
この年、スライ&ファミリーストーンは1枚のアルバムを発表します。世紀の名盤、『暴動(There’s a Riot Goin’ On))』です。『暴動』でのスライは、個人的で内省的な、重く暗いスライの姿でした。
サウンドも、どファンクになり非常に重苦しいイメージです。スライが「サンキュー」で言ってたアイデアはこれなのかって感じですが、とにかく大きな様変わりです。「ダンス・トゥ・ザ・ミュージック」ではっちゃけてたパリピー感はそこにはありません。
私は、最初に元気の良い「暴動」以前のスライから入ったので、最初はこの変わりようは戸惑いましたし、当時の論調も同様だったそうです。
今ではスライでは最も、全体でも5本指に入るほど聴いたアルバムですけどね。
It`s family affair
~(中略)~
You can`t cry `cause you look broke down
But,You are crying away `cause you are broke downそれは家族の問題だ
~(中略)~
君は泣くことはできない、だって君は壊れているようだから
それでも、君は泣きじゃくる、だって君は壊れているから(暴動:Family Affair)
志半ばで挫折したスライ
実は、1968年あたりから、スライはドラッグ中毒で悩まされていたそうで、原因は外部からの人種問題に対する軋轢で、度々脅迫を受けていたそうです。
「Thank You(Falettinme Be Mice Elf Agin)」でのメッセージは、実はもう耐えきれなくなっていたから逃げ出したかったのかもしれません、理想(パーティー)から。
「暴動」以降のスライはドラッグでどんどん「壊れて」いって、1975年の公演を最後にバンドは活動を休止してしまいました。
まとめ
いかがだったでしょうか。世紀のファンクバンド、スライ&ザ・ファミリー・ストーンの本質部分(自分ではそう思っています)にクローズアップして書かせていただきました。
結果論ですが、スライは鋼のように強い人間ではなかったようです。が、彼の発したメッセージは時代背景を考えれば非常に意義深いものだったのではないかと思います。
私が言うのもなんですが、スライはよくやったんじゃないかと思います。スライだって人は違えど、みんなと同じなんですから。
そう、
「I am Everyday People(俺はありふれた人間なんだ)」
なんですから。



コメント